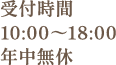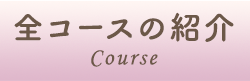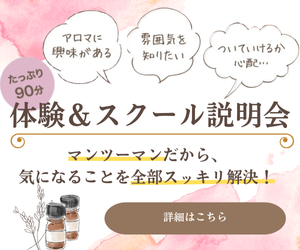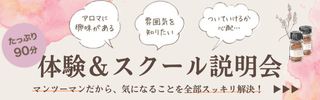私たちが生命活動を維持していくためには、内外の環境の変化や異常など、様々な刺激を素早く感じとり、適切に対応しなければなりません。
こうした情報(刺激)を受け止めている、いわゆるアンテナの役目を果たしているのが感覚器です。
皮膚感覚の種類には、
「痛覚」「触覚」「圧覚」「温覚」「冷覚」その他では「かゆみ」などが挙げられますが、
その中から
「痛み」をテーマにメディカルアロマのお話をさせていただきます。
感覚器には、様々な情報に対応する受容器細胞がありますが、痛覚には、特殊な受容器はなく、感覚神経の自由終末が侵害刺激を受けた時に生じる感覚です。「痛み」つまり痛覚は、体の殆どの部位に存在していて、表皮内だけでも約200万個の痛点が存在しているといわれています。
また視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という、一般にいわれている五感は、
ある程度他人と共有できる感覚ですが、痛覚はとてもつらいにもかかわらず、本人しか分からない孤独な違和感です。
つらい痛みへのアロマでのアプローチを考えてみたいと思います。
アロマ成分の芳香成分類としては、鎮痛作用として、以下の成分類があげられます。
エステル類、フェノールメチルエーテル類、テルペン系アルデヒド類
アロマの細かい芳香分子の中から、鎮痛作用が認められているものは
ゲラニオール 、テルピネン-4-オール、酢酸ベンジル 、サリチル酸メチル 、オイゲノール等があげられます。
そこでこれらの成分を多く含有しているアロマ(精油)をご紹介しますと、
●ゲラニオール⇒パルマローザ、ゼラニウム、ローズ
●テルピネン-4-オール⇒ティートゥリー、マジョラム
●酢酸ベンジル⇒イランイラン、ジャスミン
●サリチル酸メチル⇒ウィンターグリーン
●オイゲノール⇒クローブ
こういったアロマ(精油)が痛み緩和に役立つと言われています。