いま、医療が困難に直面しているものの一つに慢性疾患があるといわれています。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、自己免疫疾患、アトピー性皮膚炎、気管支喘息などに代表される病気が慢性疾患です。慢性疾患とは、 徐々に発症して治療も経過も長期に及ぶ疾患の総称です。
いま、医療が困難に直面しているものの一つに慢性疾患があるといわれています。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、自己免疫疾患、アトピー性皮膚炎、気管支喘息などに代表される病気が慢性疾患です。慢性疾患とは、 徐々に発症して治療も経過も長期に及ぶ疾患の総称です。
その原因には自律神経の不調が深く関わっています。
自律神経は循環、呼吸、消化、発汗・体温調節、内分泌機能、生殖機能、および代謝のような私たちの意志に関係なくはたらく不随意な機能をコントロールするはたらきがあります。
循環器系、呼吸器系等、これら生理的機能のはたらきはストレスと呼ばれる生活上のプレッシャー、それを感じたときの感覚に大きく影響を受けています。では人間はなぜストレスを感じるとこのような生理的機能が低下するのでしょうか。
そして、その症状に対してアロマはどのように役に立つのでしょうか。
人間は恐怖などのストレスを長期に渡り感じると、自律神経失調状態になります。自律神経失調状態とは、具体的には交感神経あるいは副交感神経いずれかの過剰緊張状態です。
自律神経のはたらきは、白血球のバランスを変え、免疫系にも影響を及ぼすことがわかっています。
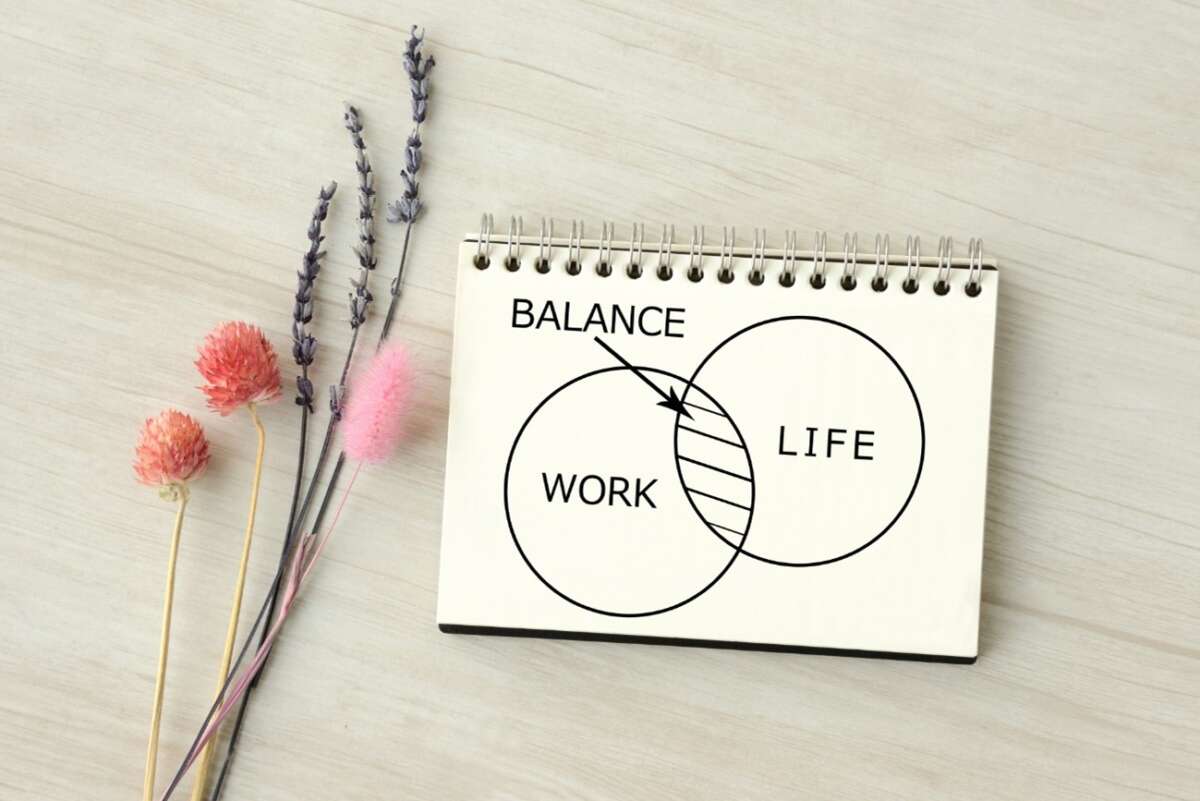
このとき白血球の1種である顆粒球(好中球・好酸球・好塩基球)が過剰になり、体内の活性酸素も増加する可能性があります。活性酸素が体内で増えすぎると、感受性の強い粘膜などの組織を破壊したり、老化や動脈硬化、がんなどの発症を引き起こす可能性が高まるとされています。
交感神経の過緊張状態へのアロマでのアプローチ
このような症状へのアプローチとして、自律神経のバランスを取り戻しながら、副交感神経を優位にし、免疫力を回復させる方法があります。自律神経のバランスを取り戻す作用はエステル類の特徴です。このようなアロマの1つがラベンダー・アングスティフォリアです。また、モノテルペンアルコール類には副交感神経を優位にする特徴があります。この特徴をもつアロマの1つがホーウッドです。したがって、ラベンダー・アングスティフォリアとホーウッドを効果的に処方することが有効です。
一方、副交感神経の過剰緊張状態になると、白血球の1種であるリンパ球(T細胞・B細胞・NK細胞等)が過剰になり過ぎることがわかっています。リンパ球は、自分の体の成分ではない種々の抗原に対して抗体を作りだす等大切な働きをしていますが、リンパ球の比率が高くなりすぎると、アレルギー症状が重症化したり、感染症にかかりやすくなったりすることが示唆されています。
副交感神経の過緊張状態へのアロマでのアプローチ
このような場合の1つのアプローチとして、自律神経のバランスを取り戻しながら、交感神経を優位にし、過剰な免疫力を適応的な範囲内に戻す必要があります。自律神経のバランスを取り戻す作用が認められているエステル類やモノテルペン炭化水素類を多く含むアロマがおすすめです。
エステル類を多く含むアロマとしてはローズやカモマイル・ローマン、モノテルペン炭化水素類を多く含み自律神経調整作用のあるアロマとして、サイプレスやアカマツ・ヨーロッパがおすすめです。

このようにアロマテラピーはストレスに対して生体反応を利用してゆっくりと治癒に向かわせていく効果的なアプローチといえます。
医学・生理学者であるハンス・セリエは、ストレスと自律神経反応の関係性を明らかにしました。特に注目すべき点は怒り、緊張、不安、喪失といった人間の感情を心理的ストレスと分類したことです。そして人間は心理的ストレスに晒されたとき、身体に負荷をかけてまでも、その環境に適応しようとする性質があるという理論を発表しました。
しかし、人間が適応できないようなストレス環境の場合、何が起きるのでしょうか。それが慢性疾患を伴う身体的ストレス反応です。これは特別なことではなく、誰にでも起こりうることです。
私たちは日頃から、ストレスの体への影響に対して対策をしておく必要があります。自律神経系に働きかけ、交感神経と副交感神経のバランスに有効なアロマを大いに日常に取り入れていきましょう。
