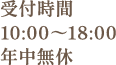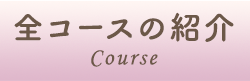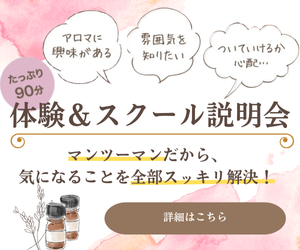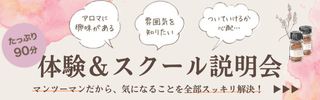アロマテラピーと聞いて、何を思い浮かべますか? 多くの方が、リラックス効果や美容効果を期待するのではないでしょうか。
確かにアロマテラピーは、良い香りに包まれて心身を癒す効果があります。しかし、アロマテラピーの可能性はそれだけではありません。海外では、アロマテラピーは医療として認められ、保険適用されているケースもあるほどです。
メディカルアロマとは、植物から抽出した精油の薬理作用を科学的に分析し、心身の健康に役立てるアロマテラピーです。精油に含まれる成分は、体内に取り込まれることで、鎮痛、抗菌、抗ウイルスなど、様々な効果を発揮します。
例えば、ラベンダーの精油には、酢酸リナリルという成分が含まれており、鎮静作用やリラックス効果をもたらします。このように、メディカルアロマでは、精油の成分とその作用を理解した上で、症状に合わせて精油を選び、安全かつ効果的に使用します。
メディカルアロマは、従来のアロマテラピーとは異なり、精油の化学的な側面を重視します。精油の成分や含有量を分析することで、より的確に心身の不調に対応できるのが特徴です。
■メディカルアロマで期待できる効果
1.痛みを和らげる
2.ストレスを軽減する
3.免疫力を高める
4.ホルモンバランスを整える
5.睡眠の質を向上させる
6.心の安定を促す
メディカルアロマは、心身の健康を総合的にサポートする、自然療法の一つと言えるでしょう。